ここでは東京拘置所における、領置(りょうち)という制度についてお答えします。
言葉の響きからなんとなく荷物置き、みたいなイメージが連想されると思いますが、「自分の部屋とどう違うの?」「ロッカーみたいにすぐに取り出せるの?」など、なかなか分かりづらい部分があると思うので、その辺りを詳しくご説明できればと思います。
そもそも勾留者はどのくらい部屋に荷物を入れられるのか

東京拘置所には棚や机など、それぞれの勾留者が自由にものを管理していいスペースが存在します。雑居(複数人での部屋)でもそうですし、独居(一人部屋)の場合なんかはもうその部屋全てが自分の空間になります。
しかし、部屋に持ち込んでいい荷物の量には制限があり、「棚とキャリーケースとカゴに入る分まで」というルールがあります。大体、大きめの段ボール2~3個分くらい、というイメージなので、制限があるといってもかなりの量がOKとされています。漫画で言えば100冊は余裕で入ります。つまりワンピース全巻を部屋に所持することも可能です。
容量を食うのは「冬服」と「雑誌」です。特に雑誌は週刊少年ジャンプやプレイボーイなどを毎週買っていると、あっという間に容量が増えます。そうすると場所がないので床に直に置くようになってきたりして、いつの間にか前述の”大きめの段ボール3つくらいルール”を逸脱することになります。
領置とは、取り出しづらい倉庫、みたいなイメージ
さて、本題の領置というのは、量が多くて部屋に収まりきらない、または部屋に置けない荷物を保管する倉庫のことを意味しています。
部屋に置けないものとしては、
- 現金(紛失防止)
- 靴(逃走防止)
- ベルト(自殺防止)
- 携帯電話
- 留置所から移動した際に東拘には入れられなかったもの(ノートなど)
などが挙げられます。
領置は留置者の部屋とは全く別の場所にあり、留置者が見たり、行ったりすることは一切できません。どこにあるのかも知りません。
領置からの取り出しには手間と時間がかかる
留置者は当然、東京拘置所の中を自由に歩き回ったりできませんから、領置に荷物を取りに行くこともできません。
そのため、領置から荷物を取り出したい時は願箋(がんせん)という願い事シートに要望を書き、親父(刑務官)に申請をする必要があります。
例えば「領置に緑色のパーカーがあるはずなので、寒いから取ってきてください」みたいな話です。
問題がなければ大体1、2日で手元に届きます。
先ほど挙げた部屋に置けないものは、当然希望しても持ってきてもらえません。保釈、釈放の際まで我慢する必要があります。
領置から宅下げはできるのか
領置からの宅下げも可能です。
例えば「現金こんなにたくさん要らないから、ちょっと嫁に宅下げしよう」とか、「携帯を調べて欲しいから弁護士に携帯を宅下げしよう」といった時には、領置から直接宅下げをすることになります。
宅下げのフローとしては通常の宅下げと同様、朝の願い事の際に申請を行います。
手元に物がないので想像(記憶)で申請しないといけないところが普通の宅下げと少し勝手が違うところです。
領置はどのくらい荷物を預かってくれる?
領置は一応ルール上は相当な量を預かることができます。実際にそんなに預けている人がいないので限界は分かりませんが、確か規則上は段ボール5~10個以上でも預かってくれたのではないかと思います。
しかし実際には「そんなに預ける物がない」「出る際に全部一気に渡されるのでそんなに保管してもらっていても持って出ることは不可能」ということもあり、領置に荷物をたくさん預けている人は少ないようです。
東京拘置所で増える荷物といえば前述の雑誌くらいしか可能性はありません。「雑誌を捨てずに全て保存したい」という人が中にはいるかもしれませんが、保釈の際に数百冊も持って外に出ることは不可能ですので現実的ではありません。親父(刑務官)も捨てろ、と言うことでしょう。

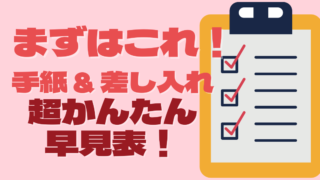

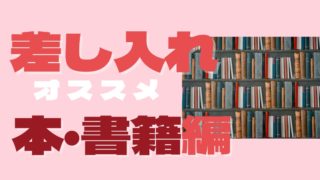






コメント